 |
| 今村 行夫社長 |
企画・編集から各種出力、複写サービスまで総合的に手掛ける富士リプロ_(本社=東京都千代田区内神田二‐八‐二/今村行夫社長)は、ドキュテック/カラードキュテックと独自開発のソフトウェアを組み合わせ、上製本の書籍をオンデマンドで提供するサービスを行っている。同社は「一歩先を考えたソフトとハード」をモットーに技術力を向上させるべく研鑚を重ね、常に「自分たちにしかできないこと」を追求し同業他社との差別化を図ってきた。今回紹介する、書籍のオンデマンド制作サービスも、こうした同社の“オンリーワン志向”から生まれたビジネスである。
|
 |
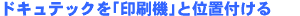 |
 |
DocuTech135(右)とColor DocuTech
60を
配置する出力部門 |
 |
 |
| 同社で手がけられた書籍の数々 |
富士リプロの現在の事業内容としては、複写、マイクロ写真、印刷の三ジャンルを柱に、コンテンツのデータ化なども行っているが、全体の六〇%が印刷である。その中で小ロットのものについては、ドキュテックによって作業を行い納品している。
印刷会社がドキュテックを導入する場合、短納期化・小ロット化などに対するいわば“オンデマンド対応”という目的があり、そのためのツールとして導入するケースが多いだろう。しかし、同社はもともと複写業からスタートした会社である。「我々は創業当時から、業態としてはすでにオンデマンドであった」と今村社長は述べる。複写業というのは、必要なものを必要な時に必要な部数だけ、より早く納めるというのが基本のビジネスだ。一八〇部欲しいと言われれば一八〇部だけを納める。そこで印刷のように「ほとんど値段変わりませんから二〇〇部刷りましょう」などということはない。しかもどんな極小ロットにも対応する。最近、合言葉のように言われている“オンデマンド”そのものを、すでに当たり前のこととして実践してきたわけだ。
では、同社がドキュテックを導入したのは、どんな目的からだったのか。
ドキュテックはそれまでの複写機に比べ高速で、A3サイズまで対応でき、簡易製本も可能だから小冊子程度ならワンパスで作成できる。しかしそのメリットだけで導入するのであれば、従来の複写業の延長にしかならないだろう。富士リプロのドキュテック導入には、同機のこうした特長を利用するだけにとどまらず、さらに独自のノウハウを付加することにより、書籍のオンデマンド出版システムを確立するという目的があった。
|
 |
同社では二〇年前から、通常は使用頻度の少ない旧字・正字・箇体字などの文字を自社で管理し、その辞書化に成功。このソフトの利用により特に中国・国文学・教本関係の分野に精通しており、組版などにおける文字の問題に関して、「富士リプロに注文すれば」という顧客の要望に応えてきた。同社は“本”の提供において、こうした長年にわたる実績を積み重ねてきている。
富士リプロがいう“本”とは、糸かがりでハードカバーのついた、いわゆる上製本の書籍であり、オンデマンドが最も望まれていながら、技術的に難しい分野であった。同社は、それをより速く、最適な部数・コストで提供するための生産ツールとして、ドキュテックを導入したのだ。
「ある老舗書店の社長の言葉を借りれば、“本”とは、そこに収められている内容もさることながら、表装のデザインや製本の具合などすべてが素晴らしく、読み終えた後も絶対に捨てられないもの。同時に、書棚に収めておいてもインテリアとして充分、価値のあるものだ。これを、ドキュテックを用いてオンデマンドで提供しようと考えた」(今村社長)
上製本の書籍というのは、それ自体が高い価値を持つものだが、何部からでも注文ができて必要な時に手に入るとなれば、より一層魅力的である。
しかし、糸かがりの上製本というのは技術的な制約も多く、ドキュテックから出力したもので実現するのは容易ではない。そこで同社では、上製本にするための印刷とはどういうものなのかを模索するところから始め、それを実現するための方策として、独自に面付けソフトを開発。これによって、通常は八面付けまでしかできないドキュテックに一六面付けまでを可能にする機能を持たせることに成功した。
富士リプロではこうして、ドキュテックを「複写機」ではなく「印刷機」として位置付けた。「メーカーから提供される機器を、そのままの形で使っているだけでは他社との差別化はできない。それをどのように利用するかがポイント。『これを使って、こんなことはできないだろうか?』と、自分たちで知恵を出しながら可能性を引き出していく」。渡邊英昭副社長はこう述べる。どんな設備をするかではなく、その使い方が問われる時代である。 |
 |
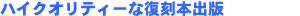 |
同社がドキュテックで手掛けた書籍の一つに、ある宗派のお寺向けの教本がある。一セット八〇巻から成り、一巻ずつケースに入った重厚なものだ。この宗派のお寺は日本全国に一〇〇〇軒ほどあり、各寺とも必ず一セットは所有している。
教本はその寺が存続している限り使い続けるものだが、何十年も使い込んでいれば汚れや染みがつき、紙もボロボロになってしまう。同じセットを新たに発注する必要が出てくる。しかし、一〇〇〇軒で使われているといっても傷みの進行度合にはばらつきがあり、すべての寺で同時に“買い替え”の需要が発生するわけではない。出版社側である程度まとまった時点で発注するとしても、せいぜい数百セット。あるいは数十セットかもしれない。八〇巻ものを数十セットなどというのは、通常のオフセット印刷ではとても現実的なコストでできるものではない。そこで出版社は、一セットからでもできるところはないかと必死に探し、その結果、富士リプロに行き着いた。上製本も可能なオンデマンドシステムを確立している同社にとって、まさに得意とする仕事であった。
出版社は、「三〇〇セットほどまとまったところで発注しようと思っているが、まだ注文が一五〇軒ほどしか集まっていない」という。それに対して「当社は何部でもできます。とりあえず一〇〇部刷りましょう。足りなければすぐに追加できます」。さらに、その本はもともとケース入りで糸かがりの上製本、一冊九五〇〇円というものであったのだが、価格を抑えるべく、「ケースは廃止し、製本方法も糸かがりでなく糊付けにし、判型も小さくしましょう」と、縮小版にすることを提案した。縮小にあたっては、何十年も前の出版物なので元原稿がないため、出版社から原本を譲り受け、すべてのページをデータ化(スキャニング)した上で、歪みを補正し汚れなどを除去した。また、文字の大きさをできる限り確保するため、周りの飾り罫なども排除した。このあたりには同社の高度な画像処理技術も見ることができる。各々のページデータが完成したら、面付けした状態でドキュテックから出力、製本して完成である。富士リプロだからこそ為し得た仕事といえる。
◇ ◇
ある出版社が古書店で発掘した本を復刻した例もある。大正末期から昭和初期にかけてのデザイン広告を集めたもので、二四冊で一セット。中に収められている広告は現代にも充分通用するデザインであり、デザイナーにとって大変貴重な資料になるということで企画された。これも原本はボロボロの状態で、すべて同社でスキャニング、修正した上で印刷した。最初は何部ほど売れるか予想が難しいため、まず一〇〇セットを印刷。すると好評を博し初版を売り切ってしまったので、後に一〇〇セット追加したそうだ。これはカラー物なので、印刷にはカラードキュテックを使った。
◇ ◇
またある時、一九三六年のベルリンオリンピック棒高跳びで活躍した大江季雄選手(一九一四〜四一)の遺族が、大江選手の活躍の記録としてとっておいた写真などを持ち込んだ。これを一冊の本にまとめたいという。「親戚に配る分、一〇〇部程度でいいのですが、本にして頂くことはできますか」。「もちろんできます」と、ハードカバー付の本にして納めたところ、非常に喜んでもらえたという。そのままにしておけば、写真などは変色したり、汚れたり破けたりしてしまう。それが「本」という形になれば、長持ちするだけでなく、記録としての価値もぐっと高まる。 |
 |
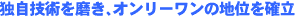 |
印刷物の小ロット化はここ数年、業界全体に見られる傾向だが、同社もその例に漏れず、数百部単位の仕事が最近特に増えているそうだ。その中には前述のような自費出版ものも少なくない。個人で書いたものを一〇〇〜二〇〇部、本にして売りたいというニーズが若い世代を中心に高まっている。少し前に、
“あなたの夢を実現しませんか”というキャッチフレーズで自費出版の広告を打ったところ、あっという間に数十通の原稿が届いたという。同社ではISBNを持っており、取次を通して流通までをサポートすることもできる。この自費出版サービスでは、受け取った原稿について、その内容に目を通した上で市場性や適正部数などを著者にアドバイスする。そして、市場性の見込めるものは同社が出版元となり制作から流通までを一貫して行っている。編集から印刷・製本まですべてのノウハウを持っているので、こうした“極小ロット”の出版においても、著者のどんな相談にも応じられるという強みがある。
今村社長は、同社の今後の方向性について、「より付加価値の高い小ロット印刷物に注力していきたい」と述べる。不毛な値下げ競争に陥っている現在の印刷業界にあって、その“泥沼”に足を踏み入れず、独自性を打ち出していくことで「顧客から本当に必要とされる企業」を目指す考えだ。
「『安い』だけを売りにしていたのでは、値段で負ければそれまで。『この仕事は、あの印刷会社でなければできない』と思われる業者にならなければならない。それには、オンリーワンのノウハウを持つことが大切だ。当社は現時点では、ドキュテックを使って上製本の書籍をオンデマンド提供するというサービス、そして外字ソフトが武器になっているが、これも永久にその独自性を保てるわけではない。したがって今持っている技術を常に進化させていくことが必要になる」
また今村社長は、「すべてのお客様が“贔屓客”になるよう、営業展開を行っている」とも語る。
「お客様というのは、潜在客、見込み客、お客、得意客、贔屓客と五種類に分けることができる。その中で“贔屓客”というのは、『他所からも印刷屋は来るけど、うちはお宅にしか頼まないよ』という、いわば心と心の信頼関係によって結ばれているお客様だ。当社はすべてのお客様と、こうした信頼関係を築きたい。これは、お客様にとって唯一の存在になることでもある」
同社では今後、カラーオンデマンドの領域にも積極的にアプローチしていく方針だ。ドキュテックとカラードキュテックを同一ライン上で、顧客の要望に応じて使い分けられる体制を構築する。そこに、オリジナル技術をさらに進化させた形で盛り込んでいく。同時に、文書をデータ化し、それを紙に限らず様々な形態で提供するという、いわばコンテンツビジネスも一つの重要な柱と位置付け、取り組んでいくという。
常に技術力向上を追求し、顧客に対して“痒い所に手が届く”サービスを提供する。それによって差別化を図り、オンリーワンの地位を確立する。これは相当な努力が必要だが、印刷会社に今いちばん求められていることでもある。 |
 |
| 資料提供:「現代出版株式会社(「印刷現代」10月号)」 |







