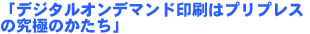
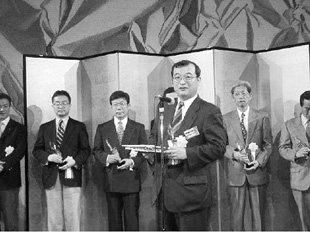 |
2000年のオンデマンドアワードでは
イノベーティブ技術部門で大賞を受賞した |
「アメリカでは一般的になっているデジタルオンデマンド印刷の普及が日本において遅れているのは、フルデジタルの意識が薄く、戦略的にデジタルデータを使おうとしていないことが大きい。最初から最後までデジタルで行うということに抵抗があるのかもしれません。また、日本語には不可欠の漢字フォントの関係で、フルデジタルにするには今のところソフト面で整っていないのも要因でしょう」と中西氏。
デジタルオンデマンド印刷機を導入し、オンデマンド印刷の取扱いを自社ホームページで唱う印刷会社は少なくない。しかしJAGATの調査によると、その中で納得のいく業績を出せているのは「2割以下」。その点についても、中西氏は厳しく指摘する。
「デジタルオンデマンド印刷は、プリプレスの究極のかたち。つまりプリプレスに強いところが有効活用できるのです。大量に刷らないと利益が出ないという従来の印刷とは世界が違い、オフセットのノウハウはデジタルオンデマンド印刷ではいきてこないのです。単にデジタルデータをデジタルオンデマンド印刷機で出力するだけでは、印刷機の構造を知らずに印刷をしているようなもの。重要なのはデータの管理能力なのです」
同社の印刷ラインも、約90人いる社員のうち、印刷工程に携わるの10人弱。一方、プリプレス工程には全体の半数にのぼる40人が就くという、「プリプレスの強い」印刷会社なのだ。
「センスの問題」とまで言い切る中西氏だが、やはり同社のデータ取り扱いは印刷の域を超えている。学術書を得意とする同社の特徴をいかし、1999年にはイギリスの学術系出版社Oxford
University Pressと提携、日本国内では未開拓だった学術雑誌のオンラインジャーナル化に踏み出した。また、「印刷物との連携」を念頭に置いた「データ提供中心のホームページ」の開設代行もインターネット事業として行っている。ここでもデザインや新機能にことさらこだわるのではなく、大切なのは「本当に利用できる」インターネットであることを強調している。
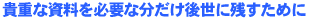
 |
| 現在の中西印刷社屋 |
しかし「結局は紙」と中西氏。デジタルデータは100年後に使用できるかどうかは分からない。「1000年後、1万年後に情報を残すことができるのは紙」だという。
「人間が滅ぶことになっても、文化は残ります。紙文書なら次の『人類』に文化を残すことはできます。1000年先をにらんで印刷物を作るというのは先代からいわれてきたこと。印刷物は時空間を超えるのです」
この想いも既に一つのかたちとして実践に移されている。同社では現在、大阪国立民族博物館の教授とともにアフリカ民謡のオンデマンド出版を実現すべく、10年がかりで民謡すべてのデータ化に取り組んでいるのだ。
「江戸時代の書物がシーボルトによってオランダに持ち込まれ、保存されていたために近代になって当時の日本を詳細に知ることができました。同じように、今は読まれないとしても数百年後に現在の民謡を知ることで文化を継承することができます。しかしアフリカでは文化の継承まで手が回らないのが現状。そこで私達が代わりに行っているのです」
数はいらない。しかしデータはたくさんある。デジタルオンデマンド印刷はそれを紙の印刷物として残すことを、現実的なレベルで可能にする。それが「オンデマンドの可能性であり、つまりその印刷技法こそ大切」と中西氏は語る。
将来的なオンデマンド印刷市場の発展に向けて
現状はオンデマンド全盛には程遠い。しかしそれは「小ロット印刷という手段がなかったために、市場がないように見えていただけで、今後つくっていけるもの」だという。DSFでの積極的な活動は、従来手法にのみ固執する体制に警鐘を鳴らす意味もあるらしい。
「必要な時、必要な量の必要な情報が必要とする人に行けばいい。いかに不要なものを減らすかという観点において、オンデマンド印刷は、生活の豊かさを保ったまま、環境も同時に守ることができます。今後、技術改良や消耗品のコストダウンなどにより、オフセット印刷との損益分岐点が500部から1000部くらいになれば普及も進むでしょう」と語る中西氏。現在はオフセット印刷が大半を占めるという同社だが、今後のオンデマンド印刷市場発展を確信し、同社の長い歴史における新たな段階確立のため、足場を固め始めている。
*オンラインジャーナル:インターネットを利用して、学術論文や学会誌などの内容をすべて掲載し、検索機能などを付けたシステムで、不特定多数の人に公開することができる。
|







