|
|

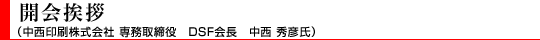 |
 |
会員の皆様こんにちは。この会も1997年がスタートの年で、9年目を迎えることができました。おかげさまで会員数も増えまして、富士ゼロックスの重鎮の方が参加されているので、当初のころと比べると、はるかに富士ゼロックスの中でも重きを成しているのかなと、勝手に自負させていただいております。
この会での重要な事は、「きちっと結果を出し、それぞれの分科会に所属して、ある程度の何か成果を出していく」ことです。その上で「新たなオンデマンドビジネスの種を見つけていこう」ということで進めています。
厳しければ厳しいほど会員が増えてくることは、結果的にはよい成果が出てきます。若手の方々に聞いても、「そのほうが刺激的でいい」ということで、この頃の皆様の勉強熱心さには感心しております。
オンデマンドもいよいよカラーに向けて完全に舵を切ったという状態になっていますので、またいいお話を聴けることを期待しております。
|
|
| |

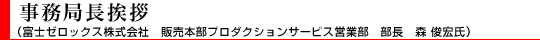 |
 |
今回は中間発表となりますけれども、ちょうど秋の完結に向けて、大事な1つの区切りではないかと、思っています。ここではっきりと方向性を出していただいて、その中で着地に向けて成果を出していただけると考えております。
昨日プレス発表をさせていただいき、この品川インターシティepicenterの19階にColor
Centerを立ち上げました。皆様とコラボレーションをしながら、いろいろなビジネスをつくり上げていく、トータルのワークフローをどんどん改善していくということを狙いにして創設されました。
オンデマンドというかたちに、どんどん市場もシフトしていくことで、さらにここ数年、大きな成長が見込めるのではないかと思っています。このDSFのメンバーの方々と一緒にチャンスをつかみ取って、成長したいと考えています。
皆様のご支援を賜りまして、まずは秋の発表に向けて、成長を期待しています。ぜひよろしくお願い申し上げます。
|
|
| |
 
 |
 |
本年度の重点施策としてepicenter内にColor Centerを設立・運営開始しております。これから2-3年の間に国内デジタルカラー市場は大きく成長していくと予測されておりますが、そのキーとなる変化は、お客様のマーケティング戦略と連鎖したデジタルプリンティングの仕組み(ワークフロー)の確立にあると思います。
たとえば、「新規顧客開拓をいかにして行うか」「個人情報はますますつかい辛くなる」といった課題に対するGIS・タウンプラス連携による新しいエリアマーケティング手法の展開や、「お客様の共感・感動を引き出したい」という「個客化」マーケティングに対するエモーショナルマーケティング手法の提案などを積極的に展開していますが、かなりの手ごたえを感じております。
Color Centerは、GA市場・顧客に対するマーケティング展開を図るグループ、業種業務特化型マーケティングを推進するグループ、ならびに全体マーケティング推進・支援を行うグループで構成されております。DSFのメンバー様とは、弊社プロダクション事業のコアパートナーとして、分科会形式やコラボレーションなどを通じて、一緒にデジタルカラープロダクション市場を造っていきたいと思っております。今後とも宜しくお願い申し上げます。
|
|
| |
 |

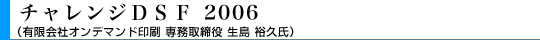 |
 |
 |
有限会社オンデマンド印刷
生島 裕久氏 |
皆さん、こんにちは。私どもは「チャレンジDSF2006」と命名して、今年の2月から新しく始まった分科会でございます。趣旨は若手による実務レベルの課題に取り組み、DSF活動のデファクトスタンダードをつくっていくという非常に大きなミッションを持っています。3回ぐらい活動をしていまして、今回は活動報告の内容を発表させていただきたいと思います。
まずは2月3日に、「カラーマネジメントと品質基準」というテーマの選定を行いました。これは実務レベルであるということ、苦手そうなテーマだということ、それからPODでの取り組みはめずらしいことなので、あえてこういうテーマに取り組みました。
「各社のカラーマネジメントの認知度を把握しよう」という目的で、カラーチャートを皆様にお配りして、結果を出して比べるということを行いました。
DDCPとインクジェット、この2つは非常によく似たような結果が出てきました。理想とするPODのカラーマネジメントは、我々の基準みたいなものと思っています。
次に、各社のPODの出力物を比較しました。これは当然CDT 60も60Vもありましたので、直接比べるのがよいかわかりませんが、もし数社で分業するような仕事とすると、これは客先に出せないというような状態でした。
いろいろと討議していく中で、「われわれは本当にCMSを知っているか、CMS自体は知っていても、全体としてどうやって活動していったら良いのかということが、まだわかってないのではないか」という話になりまして、5月19日に、文祥堂印刷株式会社様に見学に行くことができました。
この会社は、いわゆる総合印刷会社で、ドキュメントの制作から、最終的には印刷物納品までする会社です。JAGATの「グラフィックス研究会」の一員の方で、これに所属して10年あまりになる会社です。
ここの会社は、色にこだわる会社で、トータルしたCMSの管理をされています。非常にどの文献にも載っている基本的なことで、各デバイスに対してカラーマネージメントを事細かくやるというようなことを実践されていた会社でした。
今後の活動内容は、まず1つ目としてCMSのベンダーが非常に幅広くなってきたということで、オンデマンドのクオリティをどのくらいのコストで、どのくらいのものができるか?試してみたいと思っています。
2つ目が、inter-GraphicsというASP方式のカラーマッチングRIPサービスのクオリティについて検証する。
3つ目が、CMSモデルの企業調査を行うこと。
以上の3点を中心に今後進めていきたいと思っております。
|
|
| |
 |

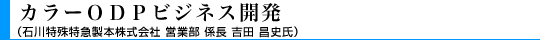 |
 |
 |
石川特殊特急製本株式会社
吉田 昌史氏 |
われわれはカラーオンデマンドビジネスの商材開発ということで、昨年度は和紙を使った商材をいろいろと作らせていただきました。今期は、分割画像を利用したディスプレー商材を今考えておりまして、中身はどういったもので作っていくかが、今後の課題になるかと思います。
1枚の写真を50分割、100分割したものをiGen3で印刷して、野球場やサッカー場での応援ボードとして、いろいろな楽しい商材として完成できたらと思っておりますので、秋を楽しみにしていてください。 |
 |
|
| |
 |

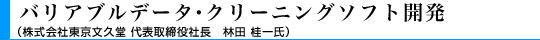 |
 |
 |
| 株式会社東京文久堂 林田
桂一氏 |
昨年バリアブルプリント用のソフトを3種類導入しましたが、実用に至っておりません。理由は、元になるデータをきれいにしないとバリアブルプリントもなかなか進まないからです。
そこで今、CSVをクリーニングするソフト開発を進めています。単にクリーニングをするだけでなく、クライアントの方が理解できるようなデータ作業まで行うソフトを作成し、それをクライアントの方に使っていただき、きれいなデータをいただくことができれば、非常に早くバリアブルプリントができるのではないかという趣旨で、今回は研究を進めています。
最初に問題点をみなさんに出していただいた結果、まず会社の住所についての問題点(DMを送るためのデータ)が整っていないことがわかりました。
それで、これを解消するのに最初に探したのが、富士フイルム様の「DTP Spider」です。このソフトはデータ変換する機能を持っており、100種類位のデータの変換が可能です。現状ではデータを抽出するということはできませんが、DTP
Spiderで取り込んで、InDesignやQuarkXPress等に直接持っていく事ができるように作られています。
2番目は、株式会社ディーエムエス様の「Address Correct」という商品です。市区町村で合併して住所が変わった時など、郵政公社のデータと照合してデータクリーニングするソフトです。ソフト代金が40万円で、年間24万円のデータ管理料、管理費が必要になります。
次に、ジャスミンソフト様のソフトで、「住所正規化コンバータ」という商品です。値段もスタンダード版購入価格が8万4千円、郵政公社のデート生成をするためのデータ更新料が年間8万4千円ということです。
ただ、この3社のソフトがすべてこのまま使えるかというと、まだ検証しておりませんので、何とも言えません。
今後われわれのニーズをとことん出して、それをこの3社にぶつけていきたいと思っています。その中で、今後開発してみたいという会社と打ち合わせをしながら、DSFのデファクトスタンダードをつくっていきたいと思っております。 |
|
| |
 |

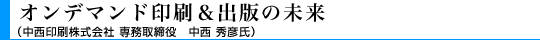 |
 |
 |
| 中西印刷株式会社 中西
英彦氏 |
今までのDSFの出版関係の研究会は、商標関係や1 to 1などには、なかなか縁が薄かったので、出版関係を何とかしようということで活動してきました。
出版社のセミナーやSF大賞、NPOとの連携などをやってきましたが、自費出版というモデル以外は、明確な収益性のあるビジネスモデルを提示できていません。
その間にも出版の電子化は進展しておりまして、オフセット印刷からいきなり電子出版という利用が増えてきました。
オンラインジャーナルにおいて、電子化の勢いは顕著に表れてきております。現在大学図書館の資料費の7割はオンラインのコンテンツ購入費という統計が出ており『紙の本』というのは既に図書館の主流ではなく、オンラインのコンテンツ購入費用のほうが上回っているという時代に入っています。
現在のオンデマンド商標出版の実例をいくつかご紹介致します。
日販BOOK-INGの特徴は、復刊ドットコムで絶版本の復刊をインターネットで呼びかけて、それをインターネットでオンデマンド復刊するというビジネスモデルです。しかし現在では、オンデマンド印刷の事業を掘り起こすという単なる再刊ビジネスになってしまっていて、ほとんどうまくいっていないようです。
次にリキエスタは、編集者が営業に頼らず自分で出したい本を作るといった趣旨のもので、オンデマンド印刷という技法を使って、安く、本当に作りたい本を作ろうという試みです。しかしこれは出版出口がオンデマンドになっただけで、印刷とほとんどコンセプトが変わりありません。
結果として、全世界で出版された本が、全部電子化されるという恐ろしい事態になっているのです。今まで日本でコンテンツビジネスが進まないと言われてきましたが、出版界でも一部関心がある方は、非常に危機感を強めています。
これからはどういうビジネスをやっていけば、出版ビジネスのほうから上っていけるかというと、1つはカラー、もうひとつは電子データです。情報を得るだけであればインターネットで必要十分であり、紙の上に載っている限り、カラーでなければ許されないことになるのではないかと思っております。そのへんについては、広島大会で報告させていただきたいと思います。
|
|
| |
 |

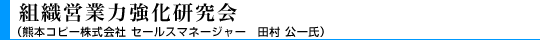 |
 |
 |
| 熊本コピー株式会社 田村
公一氏 |
ベテランの営業と新人の営業のどこが違うのか?ベテランの持っている勘、ノウハウ、経験が新人さんにないのではないか?そのへんのブラックボックスになっていたノウハウの部分を可視化しようということで、営業の標準化と売上の向上を目指していこうというのが狙いの始まりでした。
そのキーポイントとして、昨年度のプロセスの棚卸し、ツール、スキルの整理と項目別に羅列し、いろいろと研究をしてまいりました。今年の課題として、営業プロセスのオートメーション化、IT化ということを検討課題に進めております。
標準的な仕組みとしては、データベースの顧客情報を基本として、コンタクト履歴、商談のプロセス、営業スケジュールの実蹟、営業関係の進捗状況、案件成立の見込み、営業間まで共有するというものがいろいろと出てきております。
情報を共有化することで、それまで個人プレーだった営業活動の無駄を対処し、営業全体の顧客に対する戦略的な活動とチームセーリングを行うことで、いわゆる組織的な営業が実現するという大まかなあらすじになっております。
SFAのベンダーとしては、株式会社カイエンシステム開発の「BizMagicCRM」と、ソフトブレーン株式会社の「eセールスマネージャー」2社の担当者様のご意見やご質問を参考にして、研究しております。
行動実蹟、行動計画、自己管理、目標に対するスケジュール管理など、今まで取り逃していたものが、的確なサポートの元に受注が取れるように各方面のメリットというものを実感できるようなシステムづくりを今後の検討課題として、進行していきたいと思います。 |
|
| |
 |

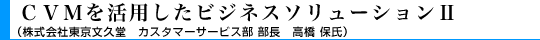 |
 |
 |
| 株式会社東京文久堂 高橋 保氏 |
上半期の活動報告ですが、今年はまた新たにターゲットを決め、ビジネスモデルを構築し、顧客とのロイヤルティー向上を図って、新規開拓につなげていきましょうということで、今年2月に7社でスタートしました。
そのうち3、4社の方は、今年から新たに参加ということで、4月に現状報告をしていただきました。全員がすでにCVMの事例を、もう2つも3つももっている会社もあれば、なかなかトップの方の号令ばかりで営業マンが動いてくれないというような会社もあり、取り組み方や理解度に非常に差があるということで、5月13日にCVMの再確認と、営業マンの動機づけということを目的に合同勉強会を実施しました。
参加企業様は12社、参加人数が41名と非常にたくさんの方に集まっていただき、アンケートを取った結果、「非常にCVMの目的や概要をよく理解できて、今後これは営業活動に有効です」と回答をいただき、成功に至りました。
今後A社様は、住宅メーカー。B社様は、不動産関係会社やホテル業界。C社様は、外資系保険会社。D社様は、都内の私立大学や信用金庫、プラントメーカー、ゼネコンなど。E社様は旅行業界、旅行会社です。F社様は、ドラッグストアや、笹かまぼこのメーカー、駅弁を作っている会社をターゲットにして、下半期活動をしていこうと進めております。
毎月の定例分科会の中で、皆様にその時点での活動状況を報告していただいて、そこでいろいろな悩みや、不足している箇所などをディスカッションして、最終の発表につなげていきたいと思っております。 |
|
| |
 |

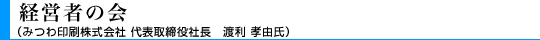 |
 |
 |
| みつわ印刷株式会社 渡利 孝由氏 |
経営者の集いということで、どうやったら儲かるか?儲けるためには何をやるかということで、1回目は、皆様に集まっていただきどんなことをやろうかという話をしました。
また富士ゼロックス様より、ダイレクトメールや、ニュースレターの定量評価手法の提案もいただきました。このようにいろいろなものを提案し、儲けられるものに関しては、本当に取り組んでいこうと思っています。できるだけ多くの情報を出して、いろいろな話をしていこうと思っていますが、あまり出し過ぎると儲けは減になってしまいますので、程々にというところでもあります。
そのようなことで、これから2カ月に1回位の割合で集まって、どんなことをして、皆様といろいろな情報提供したらいいかというようなことを勉強していきたいと思います。2回目はまた7月頃に予定しておりますので、メンバーの皆様にご案内いたします。秋の大会までにどんなことができたか、もう1度ご報告できるかと思います。
それから、国会での教科書関連法案の中で、弱視者用の教科書が提供されるということが、昨年の法案で通りました。
今年第1回目の弱視者用カラーの教科書ができました。印刷だとソフトに仕上がってしまうので、写真っぽく仕上げてくれとの要望で、弊社が今年DocuColor
8000で刷りました。年間1回だけの印刷なのですが、これが毎月あれば、iGen3を買ってもいいぐらい素晴らしい仕上がりでした。
これは第1回目の教科書関連法案の予算で取れたものです。来年度分ももう決まっていますので、また来年度のものができましたら、皆様にお見せしたいと思います。 |
|
| |
|







