|
|

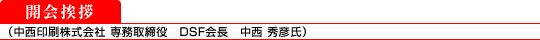 |
 |
 |
| 中西印刷株式会社 中西秀彦氏 |
皆さま、こんにちは。この会は年々盛んになっていきますが、最初のコンセプトは、「単なるユーザー会にしない、何かを残そう」ということでした。それからもう10年になります。10年を契機に、私はもうここで役員を引かせていただくのですが、その間いろいろと結果を出させていただきました。特に「大活字本」の活動は、大きな社会的なムーブメントとなっています。オンデマンド印刷を世界に知らしめる大きな役に立たせていただきました。こうやって何か結果が出る、積極的に参加することによって、始めて新しい我々の仲間も得られるということです。
DSF総会は、いつも2月の寒い時期に行われるのですが、今日は大変暑いです。ちょっと考えられません。これは「グローバルウォーム」と言われるもので、人間は産業活動をすれば地球温暖化が起きる、そしてこれが続けば、21世紀の地球文明はないかもしれないとまで言われています。それは何を意味しているのでしょうか。豊かなものを造りすぎているのです。返品率が70パーセントという時代、もし中国やインドが日本人並みに紙を使用したら、たぶん世界は真っすぐに破滅するでしょう。
いま我々ができることは、地球環境に良いことをしようということです。オンデマンド印刷は、欲しいときに欲しいだけをつくり、そして無在庫にできる。このことが地球環境にどれほど良いものか。これがやはり地球を存続していく力になるのではないでしょうか。地球のために、そのような作業を根付かせようと、これからの環境にやさしい作業として、我々は大いに推奨していいのではないかと思います。 |
|
| |
 |

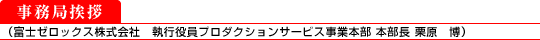 |
 |
 |
| DSF事務局
栗原 博 |
私ども富士ゼロックスは事務局として参加させていただいていますが、日ごろは大変お世話になっております。実は昨年の10月に、富士ゼロックスのプロダクションサービス事業において、営業部隊と事業本部が合体をいたしました。これにより社内の体制がスムーズになり、お客様へのサービスがいち早くできるようになりました。
これからの方向性を簡単に述べさせていただきますと、富士ゼロックスはPOD市場で、1992年に白黒のDocuTechを導入し、それがカラー化をしてiGen3につながりました。そして2007年春に、フルカラーで連張機が出ます。こういった商品を最新の技術でもって提供させていただき、また印刷業では富士フイルムの技術と私どものデジタルプリンティング技術と融合させて、お客さまの要望を従来以上に提供したいと考えております。
そしてPODビジネスをサポートさせていただく上で、商品群をただハードウエアでご提供するということだけではなくて、FreeFlowを使ったプリントオンデマンドのウェブプリント、あるいは当社のトランザクション・プリンティングというようなことで、商品プラスそのソフトウエアを充実させながら、ワークフローをトータルに活用していきたいと思っています。
また、昨年の6月に、epicenter内にColor Centerを設けました。ここではデジタルカラーの新しいノウハウやナレッジをいろいろな側面から支援させていただくことで、お客さまとのコラボレーションをもっと活発化をしていきたいと考えています。
今後の富士ゼロックスは、富士フイルムとアメリカのゼロックスと組んで、皆さまに「商品」「ソリューション」「サービス」というものを提供していくという所存です。
これからも何卒富士ゼロックスをよろしくご支援のほど、お願いいたします。 |
|
| |
 |
 
 |
 |
 |
| 株式会社トーチョウ
横山 明夫氏 |
林田様に代わりまして、今年は私がリーダーをさせていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。
今年の視点は、新たに「Webサービスを中心としたデータ作成システムの研究」ということで、FreeFlowのWebサービスを実証、検証をしながら、本来あるべきWebサービスの姿や実情を研究をしていきたいと思います。
6月の分科会まで3回ほど研究会を設けますが、まずWebサービスの現状を各社で持ち寄って話し合う、それから検証をして、Webサービスの問題点及び実用への問題提起へと、ここまで中間発表にしていきたいと思っています。その間に、富士ゼロックスのFreeFlowのWebサービスについても、いろいろと勉強していきたいと思いますが、最終的には、目的によって違うWebサービスのアウトラインを構築できたらと思っています。
なかなか結論を出すには難しい研究になろうかと思います。ただあえて言わせていただくなら、これがミックスメディアに繋がるのかなと思いますので、そういったところまで視野にいれた有意義な1年間であればいいなと思っております。 |
|
| |

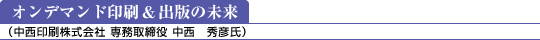 |
 |
 |
| 中西印刷株式会社 中西秀彦氏 |
今年はハイブリット出版を出版社に売ってみたいと思っています。ハイブリット出版というのは、初版はオフセットで、再版以降はオンデマンド印刷というやり方です。実はオンデマンド印刷出版という話を過去2回ほどやったのですけれども、品質上の問題点などを指摘され、散々な結果に終わりましたので、今年はそのリベンジでもあります。今、DC8000、7000がかなりよくなっていますので、また出版社を集めて、実際に売り込みに行き、反応を聞いて、反省点を見つけていくと、そういった形のセミナーをやってみたいと思います。
4月までに具体的にどういうことをするかを決めて、6月くらいに実際にセミナーをやってから、8月にフォローアップに回って、9月にまとめるぐらいか思っています。また皆さまにご協力をお願いするかもしれませんが、宜しくお願いします。 |
 |
|
| |

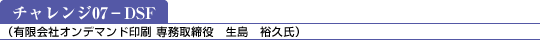 |
 |
 |
| 有限会社オンデマンド印刷
生島 裕久氏 |
今年はテーマを二つ選定して、より実務に近い形のものにチャレンジしていこうと思います。まず一つ目は「ワークフローのシナリオの構築」ということをやろうという意見が出ました。これは、メンバーの小林さんのところが、自社でそういうものを開発しているという背景と、コームラさんのところがVPA(クレオ社製バリアブルデータの処理機能)をお使いになっていて、非常に会社の中に及んで調査できるということがあります。
もう一つは、我々はやはり製品に近い部分の探究をしたいということで、VIPP(富士ゼロックス社製バリアブル用ソフトウエア)を使った製品への展開というものをやっていきたいと考えています。ただ、横山さんのところとかち合う点もありますので、今後は相談させていただくと思います。 |
|
| |
 |

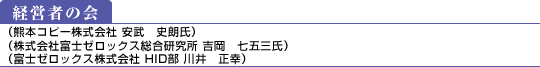 |
 |
 |
熊本コピー株式会社
安武 史朗氏 |
「経営者の会」という大きな題目を掲げて研究をしておりますが、具体的に確論の部分の勉強は、若い人たちが得意としている部分にお任せしまして、事務局の吉岡さんや私にとって、さすが年の功だと言われるような会にしたいと思っています。 |
| |
 |
| 株式会社富士ゼロックス総合研究所
吉岡 七五三氏 |
「儲けの構造研究会」という形でやっておりますが、儲かるためのHow toではなくヒントという意味です。今回は新春第一弾として「カラーを学ぶ」です。
テーマは「カラーをベースにした新しい提案営業の研究。儲かるカラー制作物のポイント」ということで、第一回目が2月20日、六本木のティーキューブ5階でやります。デザイナー、制作の部門の方もぜひ一緒にご出席ください。 |
| |
 |
富士ゼロックス株式会社
HID部 川井 正幸 |
ヒューマンインターフェイスデザイン開発部(HID部)の川井です。私のほうからは、今年のイベントとして、「伝わる、わかる、儲かる文書作成コンテスト」というものをやらせていただきたいと思います。これの趣旨は、クライアントの商品売り上げ向上のためのパンフレットを、自営業者が「顧客接点、AIDMA、文章表現」という観点から造っていくと。クライアントの意向に沿ったパンフレットにするためには、どのような文章にしたらいいのか、どのようにしたらお客様が手にとってくれるかということを、一緒に考えてみようということです。
このコンテストは、作品を応募していただくことと、審査員として応募していただくという2種類の応募の仕方があります。両方が一番いいのですけれども、そういう形でやっていきたいと思います。
どのように文書の分析をするのかというと、「お客様に手にとってもらえる文書とは?」「お客様を行動させる文書とは?」「わかる文章とは?」という、この3種類の分析を行って、定量化された評価基準にて評価をして、コンテストを行なおうという方法でやっていきたいと思います。
作品で応募していただいた方のメリットとしては、三つの分析手法を全部データとしてフィードバックさせていただきます。審査員のメリットとしては、3月に審査員の方に集まっていただきまして、そこでこの3種類の評価手法の講習会をやります。そして我々と一緒に審査をやっていただき、その結果が第一次評価ということで、第二次評価、第三次評価ぐらいまでを、8月をめどに考えております。ぜひ皆さんのご応募を宜しくお願いしたいと思います。 |
|
| |
 |

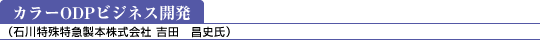 |
 |
 |
| 石川特殊特急製本株式会社
吉田 昌史氏 |
我々は今期もデジタルプリントを使いながら、おもしろい商材を開発していきます。
昨年は分割ソフトとミニ本をやりましたが、ミニ本のほうが完成品にほど遠いというお声をいただきましたので、今期は進化版として、皆さんがうなるような商材を造っていきたいと思っています。
昨年は「チョキチョキ」というソフトをつくらせていただいたのですけれども、今期は「くっつく離れる」をお題に、商材を考えていきたいと思います。
次回の分科会は、4月の24日火曜日に行いたいと思います。
頑張りますので、宜しくお願いします。 |
|
| |

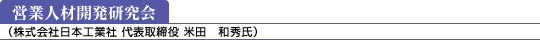 |
 |
 |
| 株式会社日本工業社 米田
和秀氏 |
皆さん、こんにちは。今年から副会長並びに初めてのリーダーを務めさせていただいております。この会は、もともとは「SFA、CVM」という、決まったツールの研究だったのですが、今回、人材開発の根本のところから、もう一度見直そうということも含めて、始めてみました。まず自己紹介を兼ねて、自分のところの会社の課題、悩み、苦しみなどを話していただいたのですが、いろいろな思いと吐露しまして、なかなかまとまりませんでした。
そこでCVMの成功事例を聞いたり、ビジネスマナーの基礎のところを想定したりと、リーダーとどのように展開していったらいいか考えたのですが、実際やってみると、ぜんぜん違う展開になってしまったというのが現状です。
実際にCVMを採用している企業に話を聞きますと、研修直後に消化不良になったり、地方の方は横展開がうまくできなかったりなど、難しい実態が浮かび上がりました。しかし、新規開拓部門を結成して、CVMを非常に有効に使われている企業さんもいらっしゃいましたし、年輩の方が受けられてもうまく展開できた企業など、非常に目新しい事例もありました。
CVMだけにこだわりたくなかったのですが、実際にいいものだと、しかしうまく伝わらない、展開できないというところが問題なので、まずはもう一回集まっていただいてヒヤリングをして、その結果をリーダーと整理して、1回目はその報告と、CVMの研修といったものを行おうと思っています。
そういうことで、今、人材開発チームは悩んでおりますけれども、何とか次に繋げていきたいと思っておりますので、宜しくお願いします。 |
|
| |
 |

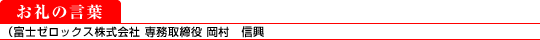 |
 |
| |
 |
| 富士ゼロックス株式会社 岡村
信興 |
本日、各チームの発表を聞かせていただきましたけれども、大変充実した内容で、この会が非常に活発に行われていて、いい結果が出ているという実感がいたしました。このドキュメントサービスフォーラムは、10年前、私どもがGA業界の皆さま方に相談させていただいてから、今年は10年目の記念すべき年ということでもありますが、2001年より研究会中心に進められて、会員数も増え、非常に会が盛会になっていると聞いております。これも会員の皆さま方の非常に熱い熱意の賜物ではないかと思いまして、心から敬意を表させていただきます。
私は40年前に富士フイルムに入社いたしまして、3年前から富士ゼロックスのお世話になっておりますが、その半分以上、印刷業界のお仕事をさせていただいております。オフセット中心の時代から、今ではデジタル印刷の仕事にも携わっていますけれども、日本はなかなかデジタル印刷が多くならないと感じていた中、業界の皆さま方のおかげで、このデジタル印刷の市場が、何となく今までとは違った大きな動きをしてくるのではないかと感じています。
10年くらい前から、いろいろなショーで、デジタル印刷が紹介されてきておりましたけれども、なかなか市場は盛り上がりませんでした。しかしここ2、3年、印刷関連のショーでは、だんだんとデジタル印刷の占めるウエートが高くなってきて、市場の中でもはっきりとその動きを感じられるようになりました。
実はここにいらっしゃるドキュメントサービスフォーラムの方々は、実際には10年以上前からデジタル印刷に関心をお寄せになって、日本の市場を切り開いていった、先駆者になっていただいた方々だと思っております。やはり先に出て苦労していた分だけ、それがバネになってさらに大きくなるのではと思います。そういう意味で、ぜひ皆さま方に、これからも先駆的な動きをしていただきたいし、私たちもできる限り一緒にやらせていただければありがたいと思います。
僭越ですけれども、これで私の挨拶にかえさせていただいて、改めて皆さんの、日ごろの私どもの商品に対するご愛顧にお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。 |
|
| |
 |

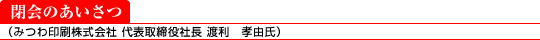 |
 |
 |
みつわ印刷株式会社
渡利 孝由氏 |
皆さん、長時間、ご苦労様でした。DSFはちょうど10年目を迎えます。10年前は30社ほどだったのですが、その2、3年後には、何と10社くらいまで減ってしまいました。そのとき残ったメンバーが、今の理事の方々です。今年は10周年ということで、安武さんと私と中西さんは、後ろから皆さんの助けをすることになりましたので、これからますます若い人たちに盛り上げていってほしいと思います。
会長が言っていますように、酒飲んでゴルフやってという会も非常にいいですけれども、何か情報を得て、仕事になればもっといいですから、できる限りの情報を取って、この会に来て良かったなというような会に、これからもますます頑張ってやっていきたいなと思っています。本当にこれからも宜しくお願いします。 |
|
| |
|







